
|
 |
山本鉱太郎 著(旅行作家) |

かつて皆既日蝕の観測で世界にその名を知られた北海道の礼文島は、夏をのぞいてはさびしいさい果ての島である。日本人が住んでいるところとしては最北端で、あとは沖合いに無人の海驢島があるだけだ。島通いの船は、海にそのすそをひたした美しい利尻富士を眺めながら一路礼文島の香深港へと急ぐ。
礼文島が近年多くの若者たちをひきつけている魅力は何だろう。それは全島にひろがる美しい草原とけんらんたる高山植物の花園である。六月の初旬になれば、レブンコザクラ、キバナシャクナゲ、ハクサンイチゲ、エゾツツジなどが咲き乱れ、七月中旬にはエゾカンゾウ、レブンウスユキソウ、トラノオなどが島を美しく装う。そしてリンドウなどの紫色の花が多くなると、礼文にもそろそろ秋が訪れる。
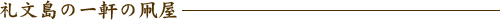
 香深という小さな港町を歩いていて、私はちょっとした発見をした。それはこんな僻地に一軒の凧屋を見つけたのである。桃岩に通じる狭い坂道をのぼっていくと、左手に小さなウィンドウのある家があり、その中に武者凧が二、三枚飾ってあった。“北海道の民芸”といえばアイヌの木彫りにアツシ織、十勝石細工、幾つかの温泉場のこけしぐらいしかないものと思っていただけに、オヤオヤと思った。絵柄といい、扁平な骨組みといい、弘前の津軽凧そっくりだ。 香深という小さな港町を歩いていて、私はちょっとした発見をした。それはこんな僻地に一軒の凧屋を見つけたのである。桃岩に通じる狭い坂道をのぼっていくと、左手に小さなウィンドウのある家があり、その中に武者凧が二、三枚飾ってあった。“北海道の民芸”といえばアイヌの木彫りにアツシ織、十勝石細工、幾つかの温泉場のこけしぐらいしかないものと思っていただけに、オヤオヤと思った。絵柄といい、扁平な骨組みといい、弘前の津軽凧そっくりだ。
礼文島で津軽凧を作っているという話はついぞ聞いたことがなかっただけに、私にとっては一つの発見であり、驚きでもあった。
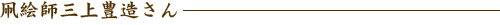
さっそく凧絵師に会ってみようと思った。ガラス戸をおそるおそるあけると、玄関先の狭い部屋が仕事場になっていて、凧絵師三上豊造さんはせっせと絵筆を動かしていた。小柄で温厚な三上さんが訥々と語るところによると、生まれは明治二十八年十月で、ふるさとは青森県の鰺ヶ沢だという。鰺ヶ沢といえば、今でこそさびしい漁師町だが、江戸時代には津軽藩最大の港町でにぎわった。
西の八幡港を守る
主の留守居は
ノー嬶守る ソリャ嬶守る・・・・
という鰺ヶ沢甚句は港町として栄えていた頃よく歌われたものだ。
「そう、私が四歳のときだったな、父に連れられて、親戚頼って、この礼文島さやって来たのは。その頃はニシンが好漁で、産卵期のころ、くきって(大群)くると、そりゃァ海がシラコ(精子)で真白になったもんだもんな。わたしは子供の頃から絵が好きで、メンコの絵を見たりして武者絵やねぷた絵をよう書いたもんだ。いわば我流でネェ。」
と、とつとつと語る。
豊造さんの父親もよく近所の子供達にダルマの絵を描いた凧を作ってやっていたが、絵はあまりうまくなかったらしい。礼文島には津軽の漁師達が大勢来ていたので、彼らの意見もとりいれて、ようやく商品となった。凧を売って生計のたしにするようになったのは豊造さんが十六、七の頃からであった。
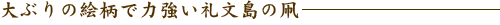
礼文島の凧は揚げ凧だから、空に揚がっても絵柄がよく見えないと意味が無い。そこで絵柄も大ぶりで、しかも力強く雄渾な感じがする。冬の休漁中に研究を重ね、今では絵柄が二十種、主に武者絵である。
 骨組みは弘前ではヒバのマサ割りを使うが、礼文島ではトドマツだ。小さな骨は山から伐ってきた木ですませ、大凧の骨は近くの製材所から買ってくる。扁平に割って釘でとめるところが、糸で結ぶ江戸凧や遠州凧とはちがう。骨組みには上等のトドマツを使わにゃ、といって、香深の愛林組合の人たちが親切にいい原木を探してきてくれると、感謝していた。 骨組みは弘前ではヒバのマサ割りを使うが、礼文島ではトドマツだ。小さな骨は山から伐ってきた木ですませ、大凧の骨は近くの製材所から買ってくる。扁平に割って釘でとめるところが、糸で結ぶ江戸凧や遠州凧とはちがう。骨組みには上等のトドマツを使わにゃ、といって、香深の愛林組合の人たちが親切にいい原木を探してきてくれると、感謝していた。
「凧は飾っとくもんでねえ、揚げるもんだ。」と、豊造さんは言う。凧が礼文島の冬空にキリキリと舞い上がると、大っぷりの武者絵がいっそういきいきと輝いてくる。
「かばふと(樺太)が見えるかよォッ、間宮海峡が見えるかよォッ!」と空に向かって呼べば、凧はワンワンとうなりをあげて答える。
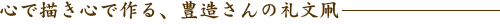
豊造さんは油絵の上手な、手細工のたいへん器用な一人息子さんがあった。それがある日、脳溢血で倒れ、札幌までヘリコプターで運んだが、助からなかった。五十三歳の働き盛りであった。老夫婦には子供はいない。孫が一人だけ。札幌の三越に勤め、時たま会えるのが唯一の楽しみだという。礼文島に根をおろした津軽凧は豊造さん一代にして滅びていくのである。
帰りしな、豊造さんは眼鏡の下で幾度か眼をしばたたかせては私の顔を探るようにみつめるのである。ひどい近眼なのか焦点が定まらないようであった。そしてこんな告白をした。
「実は私は、はじめからあなたのお顔が見えないのです。六十一歳のとき白内障で目を手術しましてネ。七十一歳のときにはいい方の目も眼底出血で今は盲も同然。長年の勘と気力で書いているようなもんでして・・・」
私が今対している凧絵師は、実は盲目同然だったのだ。私にはとても信じられなかった。この確かな筆さばきといい、この雄渾な武者絵ぶりといい、そこには微塵のゆるみも手抜かりもなく、完全そのもの。おぼろに見える影のようなものを追って、勘で書くのであろうか。心で描き心で作る。そこが名人たるゆえんでもあろう。だが豊造さんはそうした評価を否定した。まだまだ未完成だという。
 豊造さんにとってのもう一つの不満は、良質の凧紙がなかなか得られないということであった。親切な島民たちは北海道へ渡ると、紙問屋を探してはいい凧紙を買ってきてくれるが、近頃はその紙もままならない。たまたまある凧の趣味の会を通して買った千枚ほどの紙は、色がにじんでどうしようもないとこぼす。 豊造さんにとってのもう一つの不満は、良質の凧紙がなかなか得られないということであった。親切な島民たちは北海道へ渡ると、紙問屋を探してはいい凧紙を買ってきてくれるが、近頃はその紙もままならない。たまたまある凧の趣味の会を通して買った千枚ほどの紙は、色がにじんでどうしようもないとこぼす。
「一度でいい、もう一度でいいから明るい太陽が拝め、しみない紙に晴れ晴れとした気持ちで凧絵を描いてみたい」
と、豊造さんは言う。失った光はもう取り戻せないだろうが、凧紙なら探せるかもしれない、できたらその夢をかなえてあげたいと私は思った。夕日に染まった礼文島を後にしながら、盲目の凧絵師の不死身の芸に、私は改めて深く頭をたれるのだった。
|

